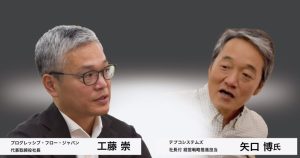
S&Tツリーを用いた全社戦略の策定と実行
株式会社テプコシステムズ 社長付 経営戦略推進担当を務める矢口博氏は、10年後を見据えた自社の野心的な変革を達成するため、全社戦略と策定と実行にTOCの考え方を活用しています。TOCの方法論に「使われず」に使いこなす矢口氏に、取り組みの背景や手ごたえ、今後の展望などを尋ねました。2回に分けてお伝えします。
注)S&Tツリー:Strategy & Tactics Tree(戦略と戦術のツリー)、TOC思考プロセスのツールのひとつ。

10年後を見据えた変革に挑む
―― 御社(テプコシステムズ、TEPSYS)では大きな変革に取り組まれていますね。そちらの概要を教えてください。

矢口氏:2021年にテプコシステムズでは、10年後を見据えた大きな変革をめざす決断をしました。2031年における姿を短い言葉で表すと、お客さまの価値創出と人財育成をTEPSYSが支えるというものです。
当社でそれまで重視された価値観は「要望の品をきちんと作って提供する」というものでした。新たに求められる価値観は「お客様にとって本当に価値のある品を利用したい時期に提供する」です。東京電力グループにおける業務変革を共創してきた当社の実績とノウハウを活用して社会に貢献し、グループ外にも大きく業務領域を拡大していくことをめざしています。
とはいえ一気にそこへ駆け上がるのではなく、変革スタート期、拡大期、成熟期、新たなチャレンジ期という4つのステップを踏みながらTEPSYSがお客さまにとって頼れるビジネスパートナーをめざすロードマップを策定しました。
――変革に取り組まれた背景には何があったのでしょうか?
矢口氏:現状のやり方のままでは、変化に富む世界の中で成長し続けることが難しい、という認識が経営層に浸透していったことです。ただ、この取り組みを検討した当時、当社の業績は必ずしも落ち込んでいたわけではありませんでした。そのために「そもそも変革をする必要はあるのか?」といった疑問や反発も少なくありませんでした。ただ、私自身には、その時点の状況が10年後も続いている保証はどこにもないはずだと考えていました。
変革の意義や目標と具体的な経営計画を結びつける
―― どのように周囲の意識が変わっていったのですか?
矢口氏:コンセプトがいくら良くても実行には、さまざまなリスクが伴います。たとえば、
- 大きな目的や方針が組織やメンバーに正しく伝わらない
- 本来とってほしい行動にならない
- 似たような施策が同時に乱立する
などです。共通の目標や全体の戦略、戦術を十分に納得できない押し付けられた気持ちのまま、あるいは消化不良の状態で目先の仕事に没頭しても足並みが揃わず部分最適にとどまりがちです。あるいは、「過去数十年の成功体験がなくなる」「これまでのやり方を否定された・・・」といった思いを抱えたまま変革を訴えてもあちこちぎくしゃくして、暗礁に乗り上げるでしょう。俯瞰したときに全社的に調和の取れたパフォーマンスに結びつきません。
それに対して、変革の前提と目的、そして施策をきちんと言語化して理解する、それを経営計画と結びつけることがうまくできれば、変革の取り組みが加速するのではないか、と考えました。いわば、自社の目指す状態を実現するための手段・目的の関係が全階層・全社員が明瞭な言語で説明することができ、具体的な実行計画に落とし込まれているという状況が理想ではないかという仮説を立てたのです。
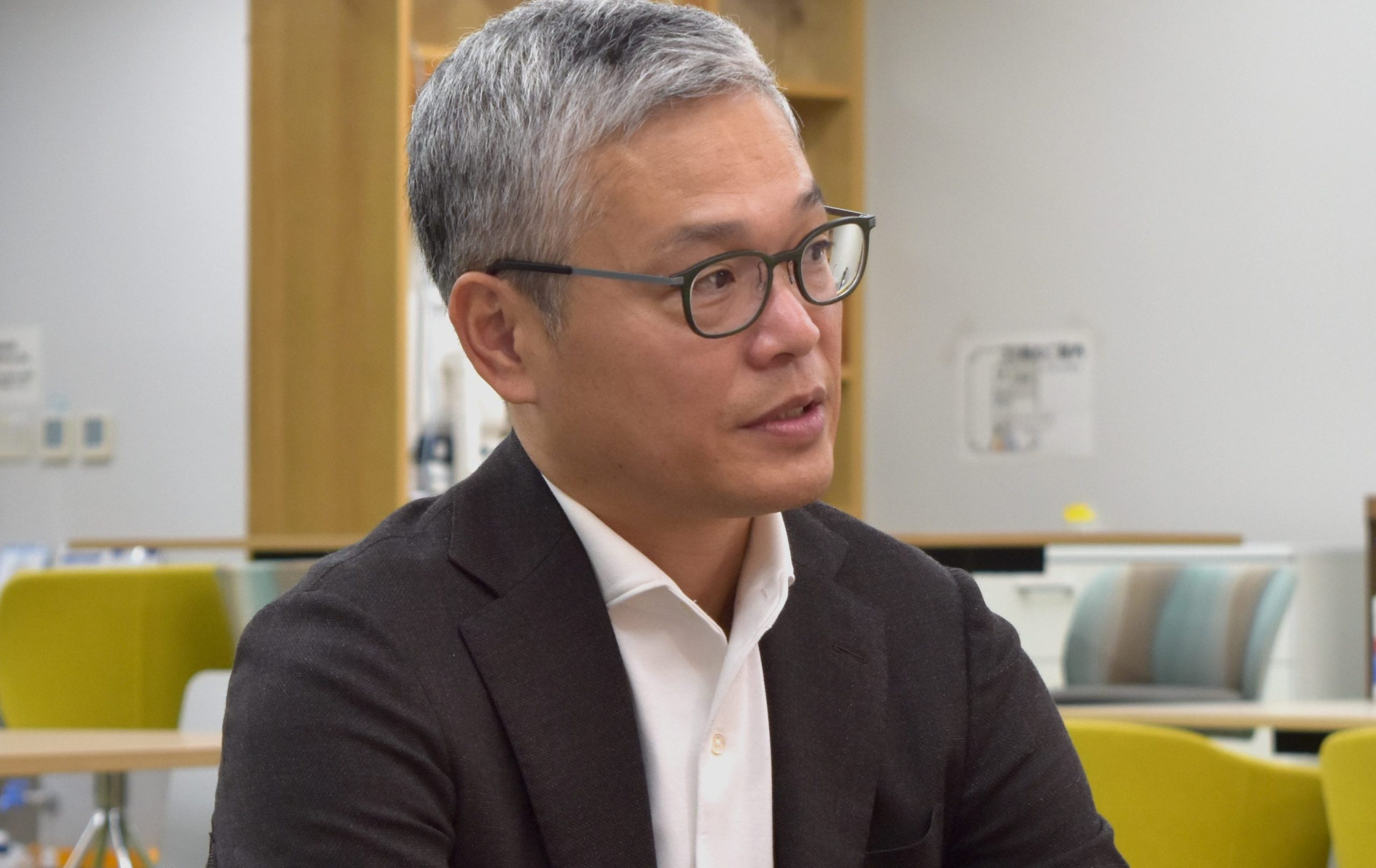
(Progressive Flow Japan Ltd.) 代表取締役社長 工藤 崇
ただ、関係者に対して「なぜ変革をしなければならないのか」「どういう姿になりたいか」「そのためには何を、何に、どのように変えるのか」というところを理解してもらうには数日程度では到底足りません。2、3年じっくり時間をかけて、時には膝詰めの合宿などを実施しながら検討を重ねてきました。
(インタビュー実施:2025年1月)
→→→ プロジェクト成功のポイントを伺った記事後編はこちら
▶️ 記事へのご意見やご感想をぜひこちらの問い合わせフォームからお寄せください。また、弊社SNSへの投稿もお気軽にどうぞ。