適用業務領域が拡がるAI
2022年11月にオープンAI(OpenAI)がChatGPTを発表して以降、AI(人工知能)、特に生成AIと呼ばれる文章や画像を作成するAIに関する開発競争が加速しています。2023年3月にはグーグルがGoogle Bardを、そして2024年2月にはさまざまなコンテンツを融合して作成するマルチモーダルAI「Gemini 1.5」(ジェミニ)などを相次いでリリースしました。するとその翌月2024年3月に、OpenAIは精緻な動画像を生成する「Sora」を開発して話題になりました。また、米国のテックベンチャー アンスロピック(Anthropic)がより自然な言語でのテキスト生成を実現する「Claude」(クロード)で参入するなど、世界各地で競争が激化しています。

こうした生成AIの能力を企業や行政機関が活用する場面が増えています。たとえば、次のようなドキュメントの作成です。
- マーケティングにおける企画やコピー文、メールなどの文案、報告書
- 人事では、求人やリクルーティング用の文章
- 営業では、顧客への各種案内や提案資料
- IT開発では、プログラムコード
- 顧客サポートを行うウェブサイトでは、問い合わせにおけるチャットボットが行う応答
AIをうまく使いこなすには?
生成AIは、機械学習と総称される情報処理のテクノロジーを主に用いて、対象とするテキストや画像、音声などの大量データをグループごとに分類、関連づけをします。学習済みの生成AIに対して、新たにデータを提示し、それがどのグループに属する可能性が高いかを判別させたり、関連するデータを選択、加工して新たなコンテンツを生成したりすることが可能です(弊社コラム「AIには苦手で人には向いていることは?」もご参照ください)。
とはいえ、ChatGPTやBardのような学習済みの生成AIを導入したからといって、すぐさまビジネスに役立つ、ということではありません。生成AIには苦手なこともあるからです。たとえば
- 学習していないことや最新の法規制などの情報に対する回答の信頼性が低い
- 金融や医療、学術分野など専門性の高い分野の回答について妄信は禁物
- 回答できない場合に、あたかも正しい回答であるかのようなもっともらしい文章を生成する事象(ハルシネーション:幻覚)が生じる
- 数学などの計算は、従来型の計算プログラムに劣ることがある
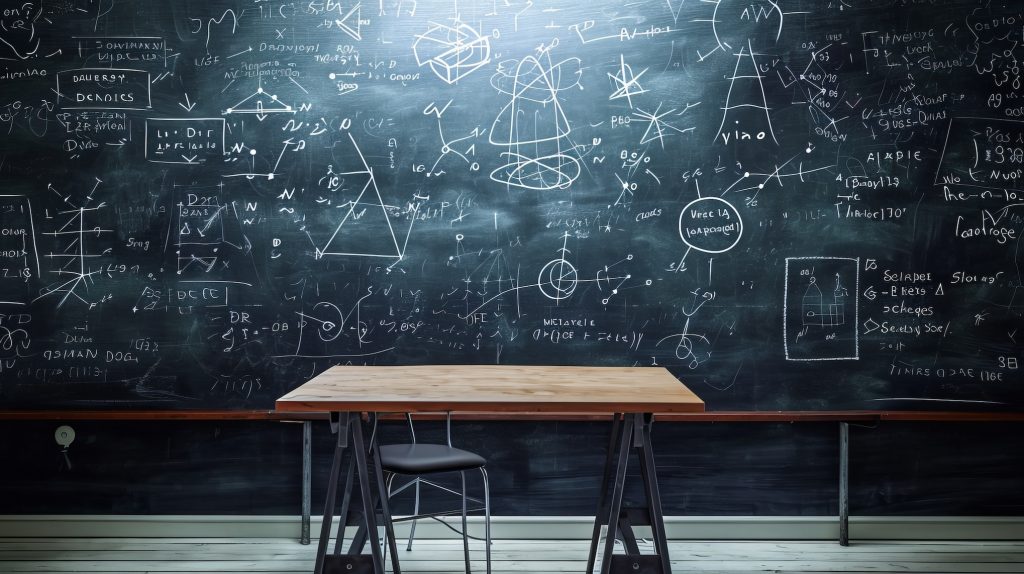
また、学習対象となるデータそのものが法規制に抵触するリスク(営業機密や個人情報の漏洩、著作権の侵害など)も指摘されます。さらに、回答の精度を高めようと計算量が増えれば、回答が得られるまでのレスポンスが低下するトレードオフが生じるほか、電力消費量の増大といった環境負荷が懸念されます。
その一方、こうした諸問題を回避、解決するための技法やノウハウが、世界各国の企業や研究機関によりこぞって開発されています。専門性の高い分野については知見を有する人材が情報を補足してから生成するようにするRAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)や、ファインチューニングと呼ばれるテクニックが研究され、業務の生産性向上に焦点を当てた、具体的なテーマを設定したPoCが各所で始まっています。
また、自社が構築したデータベースのみを学習対象として作られた言語モデルを用いて運用する生成AIや、より日本語の処理に長けた軽量な言語モデルなど、さまざまな研究開発が繰り広げられています。 生成AIが的確な回答をするように、どのような質問(プロンプト)投げかければよいか、をアドバイスするコンサルタント(プロンプトエンジニアと呼ばれることも)や、AI領域全般の導入支援を行うコンサルティングサービスも登場し、注目を浴びています。
日本と諸外国の温度差
こうしてみると現時点で生成AIは、まだ「手のかかるこども」のような印象を受けるかもしれません。
NRIセキュアテクノロジーズが日・米・豪の3カ国でおこなった「企業における情報セキュリティ実態調査2023」調査結果(https://www.nri-secure.co.jp/news/2024/0125)によると、生成AIサービスの導入率で、米・豪の約7割に対し日本は約2割にとどまり、低調であることが浮かび上がりました。

調査レポートには日本企業の導入に対する慎重さが指摘されていますが、デメリットがメリットよりも大きいという判断や印象が調査時点では多かったのもしれません。もとより(生成AIに限らず)AIをとにかく導入せよ、と煽るつもりはありませんが、こうした国による温度差の背景にあるものは何だろう、と考えさせられます。
AIの中核である機械学習やデータ分析技術は、すでに産業分野で欠かせない存在になっています。ロボット制御による工場での生産、物流倉庫内における搬送、高レベルの自動運転、小売店舗などにおける生体認証技術、医療用画像の分析による治療や施術の支援などは、一部の例です。これらのテクノロジーは、人手不足の解消というだけでなく、市場において各社が競争優位性を確保し、市場開拓の機会を拡げるための重要です。 AI分野のソフトウェア開発に取り組みたいと考えるエンジニア人材も世界的に増えています。インドの工科系大学4年生の学生にアンケート調査をしたところ、日本でAIなどのソフトウェア開発に携わりたいと答えた学生が多くいたと報じられました。
経営支援ツールとしての活用ポイント
生成AIを含めてAI一般が持つ、膨大なデータを高速に処理する性能は、人間の能力をはるかにしのぐものです。もちろん、その精度や信頼性に限界があることは否めませんが、学習を重ねていくことで、ある程度の精度や信頼性に高めていくことは可能です。誤解を恐れずに言えば、精度はそこそこかもしれないけれども、問いに対して瞬時に回答してくれるツールがこれだけ身近な存在になったインパクトが革命的と言われる一因にあります。

しかし、人間とAIの間で現時点において大きく違う点の1つは、AIが受け身である、ということです。基本的に、周り(環境)からの問いかけや刺激に対して応じてくれるだけで、能動的に動いてくれるわけではありません。「壁打ち」の「壁」といえるかもしれません。
事業開発や市場開拓といったアイデア出しの壁打ち相手としての価値はありますが、いまのところ、事業運営や経営そのものを担ってくれるわけではありません。ただ、顧客のライフイベントや購買情報などのある条件をトリガーにして動くRPA(Robotic Process Automation)と、AIを組み合わせることで、疑似的に能動的な動きを実現することは可能です。その意味でもAIは、経営の意思決定や顧客対応への専念を支援してくれる「相棒」といえそうです。
最後にあらためて、企業経営において、そんなAIと私たちはどのように付き合っていけばよいでしょうか?
ゴールを達成するために活動する組織は、メンバーが目指すべきゴールを共有し、その達成に向けて仮説を立て、検証結果をフィードバックするサイクルを回しているはずです。そして、「自ら仮説を立て、得られた結果やデータに基づいて、さらに仮説検証を重ねる人材」が活躍しやすい環境を整えることはマネジメントの役目です。そこで、仮説立案の壁打ち相手としてAIを活用することでより効率よく成果を得られるようになるかもしれません。
AIの特徴を理解し、ゴールを実現する経営の補助や支援のツールとして戦略的に活用することは競争優位を維持、向上させるうえでカギになります。 大事なのは、ツールの選択や活用を行う主体は私たち人間であることです。AIに関する情報が氾濫し、さまざまなコンサルティングサービスも登場する中で戸惑いも生じるかと思いますが、迷われた時にはいまいちど「なぜAIを導入する必要があるのか」と問い直してみてはいかがでしょう?
ぜひこちらの問い合わせフォームからご意見やご感想をお寄せください。また、弊社SNSへの投稿もお気軽にどうぞ。





